
金価格が高騰している今、「金価格が2倍になる」という噂を聞いたことのある人もいるのではないでしょうか?
金はさまざまな要因によって価格が変動するため、その一つひとつを理解しておけば、金投資で資産形成できる可能性が高まります。
この記事では、金価格の今後の予想と「2倍になる」とされる理由、具体的な投資方法や注意点などを詳しく解説します。
本記事に記載された将来の価格見通しや市場動向は、複数の業界レポートや公開情報をもとに編集・推定したものであり、いかなる投資判断を保証するものではありません。ご自身の判断と責任において参考情報としてご活用ください。
目次
金価格が2倍になる可能性はある!?今後の予想

近年、金価格が高騰しており、一部では「今後さらに2倍に上昇する」との見方もあります。その背景には、各国の中央銀行による買い増しや中国・インドを中心とした需要拡大があるいっぽうで、鉱山からの供給が限られている、という現状があるのです。
金需給のひっ迫が続くことが、価格上昇の大きな要因と考えられます。さらに、将来の金価格の行方に対して投資家の関心は高まっています。
ここでは長期・短期の目線で、金価格の今後の予想を解説していきます。
【長期的予想】5年後に2倍になる予想も!継続的な上昇の見通し
長期的には、多くの要因で金への需要が増加し続け、今後も価格の上昇が続く見通しです。
そして一部では、2030年までに現在の価格の2倍に達するとの見解も示されています。背景には、地政学リスクや経済不安によって金の安全資産としての需要が高まっていること、各国中央銀行の積極的な金購入(2022年以降の純購入量は1,000トン超)、工業用途の拡大などが要因です。
いっぽうで、金は有限な資源で埋蔵量に限りがあるため、採掘量は減少傾向にあり、採掘コストや環境規制の影響で供給が難しくなっています。
需要が大幅に落ち込むことは考えにくい中、供給面の制約が続けば金の希少性が一層高まり、価格上昇に拍車がかかるでしょう。
金価格の10年後の詳しい予想を知りたい人はこちらの記事もおすすめです。
>>金価格は10年後に2万円超える?経済動向から見る将来予測
【短期的予想】一時的な下落も…2倍になる可能性は低いと考えられる
短期的には金価格が下落に転じる局面も想定されます。そのため、直近で2倍に達する可能性は低いと考えられるでしょう。
金価格の高騰により市場に注目が集まると、初心者を含む投資家が一斉に参入し、一時的に価格が急騰する場合があります。しかし、その後に需要が落ち着けば利益を確定させるための売りが増加し、下落に転じる展開も少なくありません。
さらに、金利上昇や地政学リスクの沈静化といった要因でも価格が急落する可能性があります。実際、シティグループの分析では2026年までに金価格が最高値から約20%下落するシナリオが示されており、短期で2倍に跳ね上がる可能性は小さいと見られています。
需給バランスの変化による乱高下にも、十分な注意が必要です。
金価格は2倍になる可能性はあるのか?AIが予測!
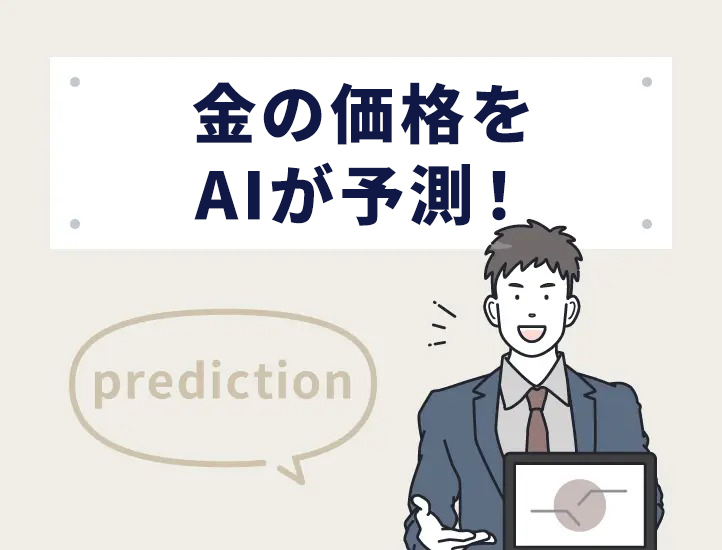
ただし、今後の予想はあくまでも予想です。これまでの動向を踏まえたうえで、弊社のアシスタントAIに予測を立ててもらいました。
今後の金価格の見通しですが、市場の動向を分析した結果、中長期的には上昇基調が続くいっぽう、短期的には調整局面に入る可能性が高いと予測しています。
中長期的な視点では、FRB(米連邦準備制度理事会)による利下げへの転換期待が金利を生まない金の魅力を高め、また中国など新興国の中央銀行による旺盛な金購入が需給を下支えしています。さらに、世界各地で続く地政学リスクも安全資産としての金の需要を根強くしており、これらが構造的な上昇要因となっています。
いっぽうで、短期的には2025年に記録した史上最高値圏での利益確定売りに加え、今後の米国の雇用統計や消費者物価指数といった経済指標の結果次第で価格が不安定になりやすく、一時的な下落も想定されます。
結論として、短期的には調整を挟むものの、数年単位で見れば強気のトレンドが継続していく可能性が高いと考えられます。
※この予測は、過去5年の価格推移などをもとに、AIが機械学習により算出したものです。ここで予測されていない外部要因によって、価格が下落に転じるリスクも十分にあるため、投資判断は慎重に行う必要があります。
金価格が「2倍になる」といわれている理由

近年、投資家や専門家の間で金価格のさらなる上昇が意識され、「2倍に達する可能性がある」との見方が広がりつつあります。ここでは、そのおもな理由を3点を詳しく解説します。
理由①2020年時点で予想されていた水準に近づいている
ひとつ目の理由は、incrementum社の『In Gold We Trust』で2020年に発表した予測値に近づいている点です。
当時、基本シナリオとインフレシナリオの両方の長期予測を立てており、それが以下となっています(1トロイオンスあたりの金価格)。
| 2025年12月 | 2030年12月 | |
| 基本シナリオ | 2,942ドル | 4,821ドル |
| インフレシナリオ | 4,080ドル | 8,926ドル |
※出典:incrementum『In Gold We Trust 2020』
実際に2025年6月時点で1トロイオンス3,435ドルを記録。基本シナリオを大きく超え、インフレシナリオに近づいています。予測は12月時点のため、今後インフレシナリオの価格まで上昇することも考えられます。
また、2025年12月までにインフレシナリオの4,080ドルに近づけば、2030年までに8,926ドルを記録する可能性も見えてきます。つまり、ここから金価格が2倍以上に成長するという見方ができるのです。
また、金の国内価格も2020年以降2倍以上に上昇しています。2020年の最高値は7,063円でしたが、2025年9月にはじめて2円台を突破。さらなる上昇が期待できるでしょう。
理由②世界的なインフレで金需要が高まっている
2つ目の理由は、世界的なインフレによって金の需要が高まっている点です。
インフレ率が急上昇すると通貨の価値が減少するため、投資家や中央銀行は資産防衛の手段として金を積極的に購入する傾向があります。
実際、2022年の世界インフレ率は約8.7%と数十年ぶりの高水準に達し、その結果として金需要が増加しました。とくに中央銀行による買い増しが、市場全体を押し上げる要因となっています。
今後はインフレ率が緩やかに低下すると予測されていますが、依然として多くの国で目標値を上回る水準が続く見通しです。物価上昇が長期化する懸念が残るなか、インフレヘッジとしての金需要は維持されると考えられます。
理由③地政学リスクの勃発・継続化が続いている
3つ目の理由は、地政学リスクの発生と長期化が金需要を押し上げている点です。
2022年に始まったロシア・ウクライナ戦争はいまだ収束の兆しが見えず、2025年中の終結も不透明な状況が続いています。
ロシアの侵攻以降、金価格は上昇を続け、2025年7月には、1グラムあたり16,250円を記録しました。ロシアの侵略前は平均6,000円台でしたが、2025年9月に2万円台を突破しており、大幅に上昇していることがわかります。
さらに、米中対立の深刻化や中東地域の紛争も重なり、国際的な緊張は高まるいっぽうです。このようなリスクは容易に解消されにくく、安全資産とされる金への需要を強めています。
地政学的な不安が長引くとの懸念から、資金流入が今後も継続する可能性は高いと考えられます。
金価格が2倍になった過去の局面

金価格は経済危機や国際情勢の変化を背景に、短期間で倍以上に跳ね上がる局面が存在します。ここでは、過去に金価格が2倍になった3つの局面を紹介します。
【1978-1980年】第2次オイルショック
1978年4月、日本ではそれまで規制されていた金取引が完全に自由化されました。同時期に第2次オイルショックが発生し、OPEC諸国は1978年末から段階的な原油価格の大幅引き上げを実施しました。
さらに、1979年1月にはイラン革命によって原油供給が止まり、世界的な原油不足とインフレ懸念が一気に高まったのです。加えて、同年12月にはソ連のアフガニスタン侵攻が始まり、地政学リスクも増大しました。
日本では比較的冷静な対応により経済への影響は限定的でしたが、国際的な不透明感から金への資金流入は急速に進みました。
その結果、安全資産としての需要が高まり、金価格は1978年10月の1グラムあたり平均1,379円から1980年1月21日には6,495円へと急騰したのです。この6,495円は、その後約40年間にわたり国内金価格の最高値として記録され続けました。
【2008-2013年】リーマンショックからの回復
リーマンショック(2008年9月)では世界的な金融不安が拡大し、投資家が資金確保を優先した影響で金価格も急落しました。
2008年10月には、1グラムあたり2,268円まで下落しています。下落前の2008年7月には、その年の高値である1グラムあたり3,339円を記録していました。
しかし、その後は各国の中央銀行による大規模な金融緩和で通貨供給が拡大し、通貨価値の下落やインフレ懸念が台頭。
さらに、欧州の財政危機や2011年の米国債信用格下げなど国際的な不安要素が相次ぎ、安全資産としての金需要が強まりました。こうした動きを背景に金価格は反発し、再び上昇へ転じています。
とくに日本では2012年末以降の急速な円安と金融緩和策が追い風となり、2013年4月には1グラムあたり5,084円を記録。リーマンショック直後の2008年10月、1グラムあたり2,268円と比較すると、国内金価格は約2倍に達したことになります。
【2020-2025年】コロナ禍から上昇が続き史上最高値を更新
新型コロナウイルス流行前の2020年1月、国内金価格は1グラムあたり平均5,524円でした。しかし、2020年初頭に起きたコロナショックで世界的な経済停滞と市場混乱が広がると、安全資産としての需要が急増し、金価格は上昇局面へ転じました。
その後も各国による大規模な金融緩和や世界的なインフレ懸念が続き、2022年のロシアによるウクライナ侵攻など地政学リスクの高まりが重なりました。
さらに円安傾向も追い風となり、金相場の上昇は持続しています。
2025年9月に1グラムあたり2円台を突破し、史上最高値を記録。コロナ前の水準からすると、3倍以上の水準へと高騰しました。
金価格を決める4つの要因
金価格は需給バランスによって決まります。需給とは、「買いたい量(使いたい量)」と「売りたい量(供給できる量)」とも言えるため、金価格は人の心理が反映されているともいえるのです。
ここでは需給バランス(金価格の変動)にとくに大きな影響を与える4つの要因を解説します。
米ドル金利の変動
銀行に「お金」を預けていると利子が付きます。つまり、預金は利息を生む金融資産です。いっぽう、貴金属の「金」自体は利息を生みません。
こうした特性の違いから、一般的に金利が上がると、利息のつかない金投資の魅力が下がるため、金価格が下がります。反対に、金利が下がると、金投資の魅力が上がるため、金価格が上がりやすくなります。
実際、金利と金価格には逆相関があるとされています。1980〜1983年、アメリカの金融政策を決める最高機関のFRBでボルカー議長による高金利政策がとられた期には、金の国際価格が大幅に下落しました。
世界情勢の変化(地政学リスク)
国際的な政治不安や戦争など、地政学リスクの高まりは金価格に大きな影響を与えます。
地政学リスクが高まる局面では、経済的な不安も懸念されます。企業に投資する株式などは不安定な状況が続くため、投資家たちは株式市場などから撤退しやすくなるのです。
いっぽう、「金」をはじめとする貴金属は、それ自体の価値は変わりません。そのため、地政学リスクが高まる状況下においては安全資産としての需要が高まり、金価格が上がるのです。このことから、「有事の金」とも呼ばれています。
実際、2022年のロシアによるウクライナ侵攻では地政学リスクが急速に高まり、金は安全資産と見なされて急騰しました。2022年2月は1グラムあたり平均6,913円だったのが、12月には1グラムあたり平均7,854円まで上昇しています。
ただし、地政学リスクが和らぐと金需要が減少し、価格が下落へ転じる場合もあるため、気を付けましょう。
インフレへの懸念
物価上昇(インフレ)が進む局面では、通貨の価値が下がるため相対的に金の価値が見直されやすく、金価格が上昇傾向になります。
金は紙幣のように際限なく発行できず、供給量に限りがあります。そのため、インフレが進んでも価値が減りにくい資産として評価されてきました。
いっぽうで、物価下落(デフレ)の懸念が強まると、安全資産としての需要が後退し、金価格は下落しやすくなります。
実際、1970年代の高インフレ期には金価格が急騰し、金価格は1971年の1トロイオンスあたり約35ドルから1980年1月には1トロイオンスあたり850ドルへと急騰しました。
反対に、1980年代前半はデフレ圧力の影響で金価格が急落しています。また、2008年のリーマンショックでは各国の大規模な金融緩和による将来のインフレ懸念が台頭し、価格は危機前を大きく上回る水準まで上昇しました。
中央銀行による金の買い入れ
近年の金価格上昇を支える大きな要因のひとつが、各国中央銀行による積極的な買い入れです。2022年以降は世界の中央銀行が毎年1,000トンを超える金の購入を行い、2024年には1,086トンに達しました。
調査会社メタルズ・フォーカスも、2025年も同規模の購入が続くと予測しています。これは年間の世界金需要の4分の1以上に相当し、年間採掘量(約3,600トン)と比較しても大きな規模です。
背景には、ドル資産への依存を減らす「脱ドル化」の動きがあります。アメリカの政策運営に対する不透明感や地政学リスクの高まりから、ドル建て資産への信頼が揺らぎ、安全資産とされる金を準備資産として積み増す中央銀行が増えているのです。
中央銀行の買い入れは当面継続する可能性が高く、金相場を下支えする重要な要因とみられます。
金が2倍になるなら…今取るべき行動

2025年時点、金価格は上昇を続けており、今後2倍に達する可能性があります。もし価格が倍増すれば、現時点で購入しておくことは将来的に大きな資産形成につながるかもしれません。
ここでは、今後の値上がりを見据えながら、どのように金を賢く買い進めていくべきかを解説します。
金価格が下がったタイミングで購入する
投資の基本は価格が下がったタイミング、つまり割安な水準で買うことです。金価格は常に上昇・下落しているわけではなく、上昇と下落を繰り返しながら価格が推移しています。つまり、金価格の上昇局面における一時的な下落は購入の好機と考えられます。
ただし、現物の金を購入するには重さによって数万~数十万円が必要となり、まとまった資金を用意する必要があります。加えて、買った直後にさらに下落する可能性もあります。
現物で買う際の注意点を把握し、検討しましょう。
毎月一定額分を購入する
金投資で一度に大きな資金を投じるのに不安を感じる場合は、定額貯金のように毎月一定額を無理なく積み立てる方法があります。
この手法は「ドルコスト平均法」といい、価格変動にかかわらず定期的に買い続けることで購入単価を平均化するしくみです。価格が高い時期には少量しか買えませんが、安い時期には同じ金額で多く購入できるため、長期的には価格変動リスクを抑える効果が期待できます。
この金の積立投資には、大きく分けてふたつの種類があります。
ひとつは純金積立と呼ばれる方法で、現物の金を少しずつ買い増していくしくみです。もうひとつは金価格に連動する投資信託やETFを利用し、毎月一定額を積み立てていく方法です。
両者の特徴やメリット・デメリットについては、次で詳しく解説します。
純金積立
純金積立は、金の現物を毎月一定額で少しずつ購入し、積み立てる方法です。購入した金は契約先の企業が預かり、一定量に達すれば現物(地金)として引き出すことも可能です。
積立期間中は自宅で金を保管する必要がなく、セキュリティ面でも安心感があります。
たとえば、三菱マテリアルでは、月々3,000円程度から始められるプランがあり、気軽に取り組める点も特徴です。
純金積立のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 少額から積立を始められる | 購入時に手数料がかかる |
| 価格変動リスクを平準化できる | 利息や配当収入は得られない |
| 現物の保管・管理を任せられる | 売買価格にスプレッド(差額)がある |
| 積み立てた金を現物(金地金)として引き出せる | NISAなど税制優遇制度の対象外 |
純金積立のメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
>>純金積立はやめたほうがいい?しくみやメリット・デメリットを解説
投資信託・ETF
投資信託やETFは、金価格に連動する金融商品です。
金そのものを保有せずに、金の値動きへ投資でき、証券会社の口座を通じて株式と同じように売買できる手軽さが特徴となります。すでに投資を行っている人にとっても、分散投資の一環として金の投資信託やETFをポートフォリオに組み込むことは効果的です。
さらに、NISAを利用すれば運用益が非課税となる点も魅力といえます。
投資信託・ETFのメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 証券口座を通して手軽に売買できる | 信託報酬などの運用コストがかかる |
| 少額から投資が可能 | 現物の金を受け取れない |
| NISAなど税制優遇を活用できる | ファンドの運用方針に左右される場合がある |
| 分散投資先として組み込みやすい | 元本保証がなく価格変動リスクを伴う |
過信は禁物!金の下落局面では売却も検討して
「金が2倍になる」という期待だけに依存するのは危険です。長期的には上昇傾向が続いてきましたが、将来の市場環境次第では大きく下落する可能性も否定できません。
相場が下落局面に入ったと判断できる場合は、早めに売却して利益を確定させることも重要です。現在の金相場は過去最高水準にあり、売却を検討する動きも見られます。
売却を考える際は、信頼できる買取業者を利用することが大切です。
「ブラリバ」は金・貴金属の取扱実績が豊富で、迅速な査定と高額買取を行っています。壊れたアクセサリーや片方だけのピアスといったアイテムでも評価対象です。
宅配や出張など複数の査定方法が用意されており、自宅にいながら取引できる利便性も魅力です。
金の買取を検討している方は、ぜひブラリバを利用してください。
長い目線で見れば金価格が2倍になる可能性がある!
金価格は長期的に上昇を続けており、将来的に2倍前後へ達するシナリオも想定されています。効率的に資産形成を目指すには、値下がり局面での購入や毎月の積立投資を活用する方法があります。
純金積立や金価格に連動する投資信託・ETFなど、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解したうえで、自身に合った手法を選んでください。
ただし、金相場にも下落リスクは存在するため過信は禁物です。価格が下落に転じた場合には、早めに売却して利益を確定させる判断も大切です。
参考文献
世界のインフレ率の推移|セカハブ
金価格推移|田中貴金属
世界の中銀による金購入、今年は1000トンと4年連続で大規模か|Reuters
『In Gold We Trust 2020』|incrementum



